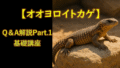皆さまこんにちは!ひとしきです。
今回は「ヒガシヘルマンリクガメの繁殖」について、解説していきます。
繁殖となると飼育の難易度が一段と上がり、適切な環境づくりや遺伝管理、産卵後の卵管理など、多岐にわたる専門知識が求められます。そのうえ本格的な繁殖に挑戦するなら、単に増やすだけでなく、次世代の健康と遺伝的多様性を守る意識も必要ですね。
本記事では、ブリーダーとしての心構えから繁殖環境の整備、そしてふ化後のケアまで網羅し、成功率を高める実践的なポイントをお伝えします。
「繁殖に挑戦したいけど、具体的に何から始めれば良いのだろう?」
「注意事項はどんなものがあるの?」
このような声にお答えできる内容となっております!
ヒガシヘルマンリクガメは長生きなリクガメであり、長いスパンでの育成計画が必要です。愛情と専門知識をもって、健全な個体を次世代へ繋げていきましょう。
ヒガシヘルマンリクガメに関する他の記事はこちらからどうぞ ヒガシヘルマンリクガメ
繁殖に挑戦する前に確認するべきこと
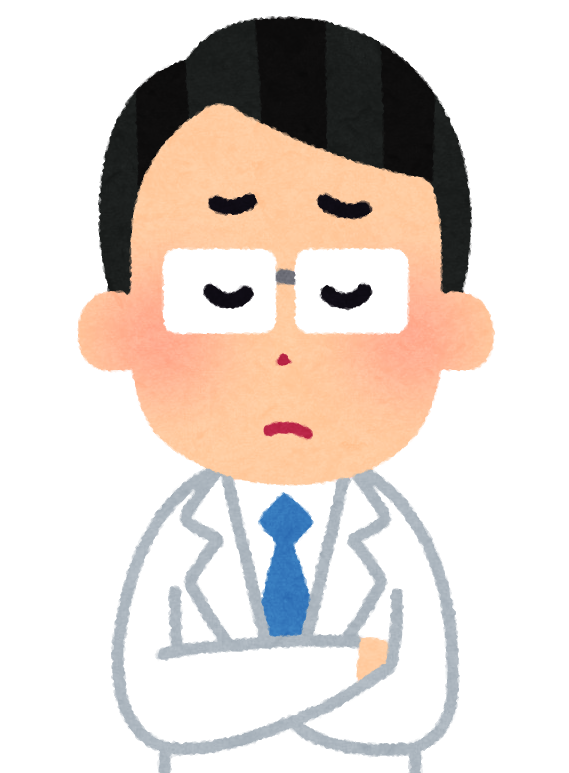
ヒガシヘルマンリクガメの繁殖に取り組む前に、まずは「なぜ繁殖したいのか」「その命をどう守っていくのか」という部分を、しっかり考えておく必要があります。
カメはとても長生きする動物で、環境の変化にもゆっくり、じっくり適応していくタイプです。その反面、生まれたばかりの稚ガメは非常にデリケートで、死亡率が高いことも知られています。つまり、生まれた命をしっかり育てられる体制が整っていないと、むしろ命を危険にさらすことになってしまうんですね。
また、ヒガシヘルマンリクガメはCITES(ワシントン条約)の附属書IIに指定されている種です。これはつまり、繁殖や譲渡に関しても国際的なルールが定められているということ。国内でのやり取りでも、法的な手続きや管理の知識が不可欠になります。
「育てきれないから手放す」といった軽い判断はできませんので、繁殖を始める前に、子ガメの行き先や育成計画も含めて見通しを立てておくことが大切ですね。
さらに、親ガメの健康状態が万全であることも、繁殖の大前提です。オス・メスともにしっかりした体格と栄養状態(特にビタミンやカルシウムのバランス)が整っていないと、繁殖自体が大きなリスクになります。メスの場合は特に、栄養不足や体力不足が「卵詰まり(産卵障害)」につながる可能性があるため要注意です。
オスで4〜6年、メスで8〜10年程度が性成熟の目安とされていますが、これはあくまで一般的な数字です。実際には甲長や健康診断の内容を参考にしながら判断するのが安心ですね。
そして最後に忘れてはいけないのが、長期的な視点です。
「産まれた子をどこで育てるのか」「複数の飼育スペースは確保できるのか」「今後の餌代や医療費にも無理がないか」など、命を育てる責任を本当に背負えるかどうかを、一度冷静に見直してみてください。
繁殖は単に「増やすための行為」ではありません。
それは、次の世代へと“健全な体と命”を受け継ぐための、大きな責任を伴うプロセスなんですよ。
環境を整える

要点まとめ
- 温度帯の管理計画(冬~春の移行)
- 広めの繁殖用ケージ or 屋内外スペースの確保
- メスが逃げ込める複数のシェルター設置
- 産卵床(湿らせた腐葉土・赤玉土、深さ10~15cm)
- 紫外線&バスキングライトで日照時間を調整
- 繁殖期に備えたカルシウム・ビタミン強化の栄養管理
解説
繁殖を目指すなら、普段の飼育環境にちょっと工夫を加えて、「交尾や産卵に適した条件」をしっかり整えてあげる必要があります。
まず大事なのが、温度管理のメリハリです。
野生では、冬眠から目覚めた春に繁殖行動が活発になりますよ。これは、気温と体温が上がって代謝が活性化することで、本能が刺激されるからなんですね。飼育下でもそれを再現するには、冬は15〜18℃くらいの低めの温度を数週間キープして、春以降に25〜30℃まで徐々に上げていくと、繁殖のスイッチが入りやすくなります。
室内飼育の場合は、冷却機器やサーモスタットをうまく使って、自然な“季節の流れ”を作ってあげたいですね。
次に大切なのが、スペースと逃げ場の確保ですね。
繁殖期のオスは、気が立ってメスをしつこく追い回すことがあるんです。ですので、広めの飼育スペースに加えて、複数のシェルター(隠れ家)を設置しておくことが、メスの安全と精神的安定には欠かせません。
そしてもうひとつ忘れてはいけないのが、産卵床の準備です。
深さ10〜15cmくらいで、少し湿り気のある土(赤玉土や腐葉土など)を敷いて、メスが掘りやすい場所を用意してあげましょう。夜間や早朝に産卵する傾向が強いので、昼間だけでなく夜間の温度や湿度管理も気を抜けません。
紫外線ライト(UVBライト)と日照管理も超重要です。
ビタミンD₃の合成を促すことで、卵の殻を作るカルシウム代謝がスムーズになりますし、自然な季節感の演出にもつながります。照明のオンオフ時間を少しずつ変えて、春らしいリズムを演出するとより効果的ですよ。
もちろん、栄養面の強化も忘れずに。
産卵前後は特に、カルシウム・ビタミンの摂取量を意識して、サプリメントなどでしっかり体づくりをサポートしてあげましょう。
交配方法と手順

ヒガシヘルマンリクガメの交尾行動が活発になるのは冬眠明けの春先〜初夏が中心です。ブリーダーとして交配を成功させるには、まず十分に成熟したオスとメスを選んで、数日〜数週間ほど同居させながらお互いを慣らしていくところからスタートしましょう。
交尾の時期になると、オスはメスに対してちょっと激しめのアプローチをすることがあります。たとえば、メスの後肢に噛みついたり、甲羅に体当たりして追いかけるなどですね。これは一見乱暴に見えるかもしれませんが、自然な求愛行動の一部なんです。
ただし、メスに傷がついてしまうほど追い回すようなら、無理をさせずに一時的に隔離する判断も必要です。リクガメの気持ちも、それぞれ違いますからね。
交尾がうまくいくと、オスはメスの背中に騎乗姿勢をとって、交尾中に高音で「キッ、キッ」といった短い鳴き声を出すこともありますね。
この交尾行動は、個体によって数分で終わることもあれば、10分以上続くこともあります。
交尾が終わっても、すぐに産卵というわけではありません。メスは数週間〜数か月かけて卵を体内で成熟させていくので、のんびり構えて見守りましょう。一度の交尾で複数回産卵することも珍しくなく、飼育下では年に2~3回の産卵例もあるため、産卵床は交尾後も長期間にわたって準備しておくのがおすすめです。
さらに、血統やモルフ(色・模様の遺伝的特徴)をしっかり管理したい場合は、交配前に親ガメの遺伝的な情報(ホモ・ヘテロの遺伝子構成など)を調べておくことが大切です。最近は遺伝子検査サービスや血統登録制度も普及していますので、将来的に計画的なブリーディングをしたい方には大きな味方になりますよ。
卵の管理

ヒガシヘルマンリクガメのメスが産卵を終えると、ちゃんと自分で巣穴に土をかけて埋め戻す行動を見せてくれます。自然な行動なので見守ってあげたいところですが、飼育下では卵を見つけたら早めに取り出して、人工ふ化に移行するのが一般的です。
掘り出すときには、卵の上下の向きを絶対に変えないように注意してください。胚が固定されているため、回転させると成長が止まってしまうリスクがあります。
なお、自然孵化(巣に埋めたまま)を狙う方法もありますが、室温や湿度が安定しない環境では失敗のリスクも大きいので、インキュベーター(人工孵化器)での管理が安定しておすすめですね。
孵化器での管理
温度
28~32℃の範囲で管理するのが基本です。温度によってふ化にかかる日数や生まれる子の性別比が変化します。ヒガシヘルマンリクガメは「TSD(温度依存性性決定)」という特徴があり、高温気味に管理すると雌が生まれやすくなる傾向があるんですよ。
湿度
湿度は70~80%くらいをキープするのが理想です。乾燥しすぎても過湿すぎても卵にダメージが出てしまうので、毎日霧吹きで調整するのがコツです。
孵化期間
ふ化には約50〜90日かかります。温度が高いほど短く、低めだと長くなる傾向があります。焦らずじっくり待ちましょう。
培地には清潔なバーミキュライトやパーライトなどを使うのが主流です。カビや腐敗を防ぐためにも、通気性を確保しつつ、過湿にならないようにこまめにチェックしたいですね。
インキュベーター内で結露や異臭が出ていたらすぐ換気や培地交換を行ってください。
また、卵の中の胚の発育状況を観察することもできますよ。表面が白く濁ってきたり、血管の発達が見える卵は“受精卵”の可能性が高いですが、一方で、カビが生えたり、変色した卵は無精卵や胚の停止が疑われるため、放置せず早めに取り除いて、他の卵を守るようにしましょう。
ふ化した後

ふ化後の稚ガメは、見た目はかわいらしくても、生理的にはとても不安定な時期を過ごしているんです。ここからは、そのデリケートな時期を安全かつ健康に乗り切らせるための管理ポイントを、ひとつずつしっかり掘り下げて解説していきますね。
最初は餌を与えなくてもOK
ふ化した直後の仔ガメは、お腹の下に卵黄嚢(らんおうのう)という黄色い袋を抱えています。これは卵の中で使わなかった栄養分が蓄えられているもので、ふ化後1週間ほどの生命維持をまかなってくれるんですよ。
この時期は、まだ消化管も未発達なので、無理に餌を与えないようにしましょう。むしろ、落ち着いた環境で体力を回復させることの方が大切ですね。
脱水は命取り
「餌はいらない」と言っても、水は別です。卵黄嚢があるとはいえ、呼吸や代謝で少しずつ水分は失われていきますし、ふ化後すぐに活動的になる個体もいるんですよ。
だからこそ、浅くて自力で出入りできる水場を必ず設けておきたいですね。容器の深さは甲羅の高さの半分程度までが目安で、底に小石や滑り止めを敷いてあげると、足を滑らせず安心して出入りできるようになりますよ。
衛生環境が超重要
ふ化直後の甲羅は、まるで爪が乾ききっていないような状態で、まだしっとりと柔らかく傷つきやすいんです。当然ながら、外傷や感染にも弱い状態ですので、雑菌を防ぐ環境管理がカギになります。
清掃が簡単で衛生的な飼育ボックス(プラケースなど)を使い、床材はキッチンペーパーなど吸水性のあるものを使うのがベストです。
温度は28〜30℃前後、湿度は60〜70%を保ちつつ、毎日様子を見て交換してあげてくださいね。汚れやアンモニア臭が出る前に交換することが、病気の予防には一番の近道です。
餌付けのスタートは「腸の準備」が整ってから
卵黄嚢が吸収され、子ガメがよちよち歩き始める頃になると、そろそろ給餌開始の合図ですね。消化器はまだ発展途上なので、消化しやすく、栄養価が高すぎないものを選ぶことが重要です。
おすすめは、刻んだ柔らかい野草(タンポポ・ハコベ・クローバーなど)やベビーリクガメ用の高繊維フードを、少量から試していくこと。
モロヘイヤや小松菜などの葉野菜もいいのですが、シュウ酸を多く含む野菜(ほうれん草など)は避けてくださいね。シュウ酸はカルシウムと結びついて吸収を妨げてしまいます。
個体差が出やすい時期こそ、観察が命
ふ化直後は、体格差・活力差がはっきり出やすい時期です。元気な個体はすぐに餌を探しに行きますが、慎重な個体や体力の少ない子は食べ損ねてしまうこともあります。
そのため、初期の段階では個体ごとに餌の量を管理したり、小さなグループに分けて給餌するのもひとつの方法ですね。
将来の血統管理のために、個体識別は早めに
繁殖を継続していく方にとっては、どの個体がどの親から生まれたのかを記録しておくことが将来的に非常に重要になってきます。
甲板の形や模様である程度識別できる場合もありますが、写真記録・マーキング・マイクロチップのいずれかの方法を組み合わせておくと安心ですよ。
また、モルフの傾向(色や斑紋)が見えてくるのは、早い個体でふ化数週間後、遅くても数か月以内には明らかになってきます。観察日記をつけておくと、後々繁殖ペアを組むときに非常に役立ちますね。
まとめ
ヒガシヘルマンリクガメの繫殖について解説しましたが、いかがだったでしょうか?
繁殖がうまくいって、新しい命が生まれる瞬間というのは何にも代えがたい感動がありますよね。それだけに、その子ガメたちをどう育て、どんな未来を用意するかという長期的な視点もとても大事になってきます。
たとえば、「スペースが足りなくなったら?」「もし譲渡するならどんな相手に?」といったことまで、事前に考えておくことが大切です。
時間の流れを見据えた育成計画こそが、繁殖の要というわけですね。
それではまた、別の記事でお会いしましょう!
出展
- IUCN SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group [2020]
- CITES Appendices [2022]
- 日本爬虫類学会「飼育ガイドライン」[2021]
- AZA Care Manual for Testudo Species [2018]
- Reptile Breeding Journal [2021]
- 『リクガメ繁殖入門』[爬虫類専門出版, 2020]