皆さまこんにちは!ひとしきです。
今回は「ヒガシヘルマンリクガメの飼育方法」について、解説していきます。
飼育に慣れてくると、新たなトラブルや課題に直面することが多いのが飼育管理の難しさですよね。基本的な飼育方法は理解していても、成長に合わせた環境のアップグレード方法や病気の予防・対策は奥が深く、難しい課題です。
この記事では、栄養バランスの取り方、そして発生しやすい病気やケガの対策まで、総合的に解説します。
「注意すべきポイントや病気がまだよく分からない…」
「リクガメ飼育をさらに充実させたい!」
このような声にお答えできる内容となっております!
より安心して日々の管理や緊急時の対応ができるように専門的な知見を集約しました!ぜひご覧ください。
ヒガシヘルマンリクガメに関する他の記事はこちらからどうぞ ヒガシヘルマンリクガメ
飼育環境を整える

ヒガシヘルマンリクガメには温度帯を分けたケージ設計と、UVBライト・多層床材・保温設備の適切な導入が必要です。自発的に快適な場所を選べる環境づくりが健康維持のカギになりますね。
必要な飼育環境リスト
- 広めの専用ケージまたは囲い
- 複数の温度帯を作れるヒーター・保温器具
- 高品質で定期交換が必要なUVBライト
- 保湿と乾燥を両立できる多層構造の床材
- シェルターや登れる高低差のあるレイアウト素材
- 給水用の浅皿と餌置き場
- 温度・湿度管理ができるサーモスタット付き制御装置
解説
前回の記事でもお話ししましたが、ヒガシヘルマンリクガメを飼育する場合、ただケージを用意するだけではなく、温度帯を複数設定できる環境を作ることがとても重要です。たとえば、バスキングエリアは35℃前後、くつろぎやすい中間のエリアは25~28℃くらい、夜間に少し涼しくするエリアは18~22℃…というように、ケージ内で温度にグラデーションをつけてあげると、リクガメが自分で快適な場所を選んで過ごせるようになるんですね。
また、紫外線ライト(UVBライト)は、照射量が安定している高品質タイプを選びましょう。メーカーによって違いはありますが、3~6か月ごとに交換時期をチェックして、紫外線がしっかり届く状態を保つことが大切ですね。
床材については、ヤシガラ土や腐葉土を下層に、バーク(樹皮チップ)を上層に敷く多層構造にすると便利ですよ。保湿と乾燥のバランスがとりやすくなりますし、リクガメ自身が「今日はちょっと湿ったところがいいな」といった具合に、自分で場所を選べるようになるんです。
もし屋外飼育を考えているなら、季節や地域によって寒暖差が大きくなることも多いので、可動式の保温器具や簡易的なシェルターを用意しておくと安心です。自然の中でのびのび過ごさせたいときでも、きちんとリスク管理しておくことが、リクガメの健康維持につながるんです。
エサの種類と給餌方法

ヒガシヘルマンリクガメには、野草・葉野菜を中心とした高繊維の餌が最適。補助的にペレットやカルシウム源を加え、給餌頻度は1日1回程度が目安。清潔維持も健康管理に欠かせません。
エサ
- 野草系:タンポポ、クローバー、オオバコ、ハコベ など
- 葉野菜系:チンゲンサイ、サニーレタス、小松菜、モロヘイヤ など
- 補助食:リクガメ用ペレット、乾燥野草ミックス
- カルシウム源:カルシウムパウダー、カトルボーン(イカの甲)
給餌方法
ヒガシヘルマンリクガメは、植物食傾向の強い雑食性ですので、飼育下では繊維質が豊富な野草や葉野菜を中心に、バランスよく組み合わせた給餌が理想です。
たとえば、野草ならタンポポ(キク科)、クローバー(マメ科)、オオバコ(オオバコ科)などが定番で、栄養バランスも良く、カメたちの食いつき(嗜好性)もバッチリです。市販のリクガメ用ペレットフードも便利ですが、それだけに頼るのではなく、あくまで補助的に使うのがポイント。主役はあくまで“自然に近い草”なんですね。
それと、成長期の個体に限っては、ごく少量のフィーダー昆虫(デュビア、シルクワームなど)をカルシウム補給目的で与える飼育者もいます。ただし注意が必要で、動物性の餌を与えすぎると、肥満や腎臓への負担が出てくることもあります。ごく少量でじゅうぶんですよ。
給餌の頻度は、1日1回〜2日に1回程度が基本ですが、個体の年齢や状態によって調整してあげる柔軟さも大事ですね。
食べ残しやフンは、毎回しっかり片付けて、常に清潔な環境を保つことが病気予防の第一歩になりますよ。
飼育中に注意するべきポイントと対策

夏場の高温対策
ヒガシヘルマンリクガメの適正飼育温度は日中で25〜32℃、バスキングスポットで34〜36℃が目安ですが、日本の夏はそれを超えて40℃近くになることもあるため、屋内でも高温障害のリスクがあります。
換気扇付きのケージやUSB駆動の小型ファンを使って空気を循環させ、熱がこもらないようにしましょう。どうしても温度が下がらないときは、冷凍ペットボトルをタオルで巻いてケージ外に設置する応急処置も有効です。
また、ケージ内の温度を把握するには、最低2か所以上(バスキングエリアとクールエリア)に温度計を設置するのが理想です。湿度との兼ね合いもあるため、湿度計付きのデジタル温湿度計があると便利ですよ。
餌のバリエーション確保
ヒガシヘルマンリクガメは、偏食傾向が出やすい種でもあります。これは、嗜好性の高い食材(例えばチンゲンサイやペレット)ばかり与えることで、特定の餌しか受け付けなくなる“食性固定”が起こるためです。
野草をベースにしつつ、週単位で餌の種類をローテーションするプランを作るとよいでしょう。たとえば、今週はオオバコ・モロヘイヤ中心、次週はハコベ・サニーレタス中心…という感じですね。
また、ビタミンAやEの欠乏は視力低下や皮膚の乾燥、免疫低下にもつながるので、βカロテンを多く含む植物(ニンジン葉やモロヘイヤなど)も取り入れてください。
水分補給の習慣づけ
リクガメは腎機能が弱く、脱水に非常に敏感です。とくに高温期や換気重視の乾燥した環境では、目に見えにくい形で体液が失われます。
毎日決まった時間に水浴びの時間を取ることで、皮膚からの吸水+排泄促進+ストレス緩和の効果が期待できます。週1〜2回はぬるめ(28〜30℃)の温浴を5〜10分行い、排泄物のチェックも兼ねると良いですね。
また、湿度は日中40〜60%、夜間50〜70%程度をキープするのが理想的で、ケージ内の乾湿差を意図的に作るのもおすすめです。
甲羅の変形(ピラミッディング)
ピラミッディングの発症は、高タンパク・低繊維の食事と乾燥した飼育環境が主因です。実際、湿度40%未満かつ成長期に過剰なペレットを与えた個体では、著明な甲羅変形が報告されています。
解決策としては、
- 乾燥しやすい時間帯(昼間)は適度な加湿
- 成長期(1歳半〜3歳)のタンパク質摂取量を厳密に制限
- カルシウムとリンの比率を2:1に保つ
などの対策が有効です。成体になっても進行は止まらないため、幼齢期からの管理がカギを握ります。
通気と衛生管理
リクガメのケージは、高湿度+不十分な換気=カビ・細菌・真菌の温床になりがちです。とくにココピートや腐葉土系床材を使っている場合、通気性を確保しないと悪臭や皮膚病の原因になります。
ケージの通気性を保つには、
- 側面や上部にメッシュ通気口を設置
- 毎日換気時間を確保する(10〜15分の開放)
- フン尿、食べ残しはその日のうちに完全撤去
といった対策が効果的です。衛生管理は、感染症だけでなく、寄生虫リスクの低減にも直結します。
ストレス源の把握
リクガメは見た目ののんびりさに反して、環境変化に敏感な動物です。日常の中での小さなストレスが食欲不振や拒食、行動異常につながることもあります。
ストレス要因としては、
- ケージを頻繁に移動させる
- 室内で犬猫がケージに干渉する
- 人間の視線・音・振動が多い場所に置かれている
などがありますね。シェルターを2つ以上設ける、静かな部屋にケージを設置するといった対応が、リクガメの“安心領域”を保つ上で重要です。
甲羅・皮膚の定期観察
皮膚炎や甲羅の白化、びらん(ただれ)は早期発見できれば完治が見込める病気です。ただし放置すると全身感染や壊死に進行するケースもあります。
チェックポイントとしては、
- 甲羅表面に白っぽい斑点や柔らかい部分がないか
- 四肢の付け根、口角、鼻孔に炎症がないか
- 皮膚の乾燥や剥がれが過剰でないか
などを週に1〜2回観察しましょう。写真記録を残しておくと、微細な変化にも気づきやすくなります。
トンネルや高低差のレイアウト
ヒガシヘルマンリクガメは、地中を掘る・登る・くぐるといった行動を通じてストレス解消や運動不足解消をしています。
ケージ内に傾斜のある木片や低めのステップ、半トンネル状のシェルターを取り入れると、自然な動きが出やすくなりますね。ただし、傾斜が急すぎたり、高さがありすぎたりすると転倒や落下のリスクが出てくるので、カメの甲長以下の高さを目安に、安全性をしっかり確保して設置しましょう。
冬眠管理と体調チェック
ヒガシヘルマンリクガメは地中海性気候に適応した種で、野生下では明確な冬眠期があります。室内飼育でもこのリズムを模倣することが、繁殖行動や長期的な健康維持に寄与するんです。
ただし、冬眠は体に大きなストレスを与えるため、開始前に「準備期間」を設けることが推奨されます。餌を与えるのは最低でも2週間前までとし、腸内の内容物を排出させることで冬眠中の腐敗リスクを下げます。
体重は0.5g単位で記録できるスケールを使い、冬眠中に週1で記録するのが理想的です。10%以上の減少が見られた場合は、すぐに冬眠を中断し、保温下で回復させる必要があります。
冬眠は自然な生理現象ですが、体力のない若齢個体や病歴のある個体には実施しない方が安全ですよ。
爬虫類専用獣医師の確保
リクガメは哺乳類とは全く異なる代謝と解剖学を持っているため、一般的な動物病院では正確な診断が難しい場合が多いです。
住んでいる地域に「爬虫類専門」「エキゾチック専門」と書かれている病院があるか、あらかじめ調べておきましょう。
また、年に1回の健康診断(糞便検査・触診)も重要で、寄生虫や初期の栄養障害を見逃さないために役立ちますね。
罹患する可能性のある病気と対策
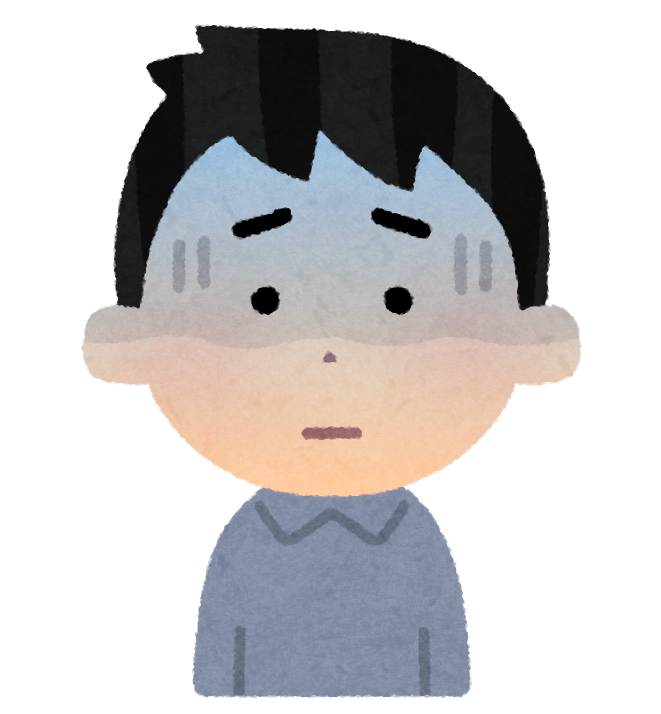
呼吸器感染症
ヒガシヘルマンリクガメがくしゃみをしたり、鼻水が出ていたり、口で呼吸していたら要注意です。この症状は呼吸器感染症の典型的なサインですね。湿度の乱れや通気不良、低温環境がきっかけで免疫が下がり、細菌やウイルスにやられやすくなってしまうんです。
軽症なら環境を見直すだけで回復するケースもありますが、進行すると肺炎に発展してしまい、食欲不振や元気の低下につながることも。だからこそ、日頃の観察と早めの対処が大切なんです。症状がひどくなる前に、爬虫類に詳しい獣医さんへ相談することをおすすめします。
甲羅の壊死・腐皮症
甲羅が白っぽく濁ったり、柔らかくなっていたり、ただれているように見えたら、「シェルロット」と呼ばれる病気かもしれません。主に細菌やカビ(真菌)による感染が原因です。
床材がいつも湿っていたり、ケージ内が不衛生だと発症リスクが一気に高まります。初期のうちは、消毒と乾燥環境の見直しで改善できることもありますが、深くまで感染すると外科的な処置が必要になることもあります。
予防のポイントは、通気と清潔の両立です。ちょっとでもおかしいなと思ったら、早めに対処しましょう。
代謝性骨疾患(くる病)
甲羅や脚が変形してきたら、カルシウムやビタミンD₃の不足が原因の「MBD(くる病:代謝性骨疾患)」かもしれません。
UVBライトが不十分だったり、カルシウムの少ない食事が続くと、骨がもろくなって、甲羅のピラミッディング(ボコボコ)や四肢の変形が出ることがあるんです。
予防のためには、毎日の紫外線照射(UVBライト)と、カルシウムのしっかり摂れる餌のバリエーションがとっても大切です。リンとのバランス(Ca:P比)も意識すると、より効果的ですよ。
口内炎
口の中が赤くなっていたり、なんだかエサを食べにくそうにしていたら、口内炎ができているかもしれません。
小さな傷やビタミン不足、餌の内容が合っていないことが原因で、細菌感染が引き金になることが多いんですよ。軽度なら消毒や投薬で治ることもありますが、放っておくと摂餌困難になって体力が一気に落ちてしまうことも…。
毎日、口のまわりを軽く観察して、ちょっとした変化に気づけるようにしておくと安心ですね。
消化器障害
リクガメの便がゆるくなったり、逆に出にくくなったり、なんだか食欲が落ちているな…と感じたら、それは消化器系のトラブルかもしれません。
原因として多いのは、運動不足・食物繊維の不足・床材の誤飲・寄生虫感染などです。とくに誤って床材を飲み込んでしまうと、腸閉塞などのリスクもあるので注意が必要ですよ。
対策としては、野草などの繊維質をしっかりとって、水分補給もこまめに。便に異常が見られるときは、寄生虫検査や獣医師の診察を早めに受けるのが安心です。
まとめ
ヒガシヘルマンリクガメの飼育方法について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
健康状態を守るには、日頃の観察を丁寧に行い、些細な異変でも早めに対処することが非常に重要です。特に、長寿なリクガメだからこそケガや病気のリスクは年単位で蓄積しやすく、飼育歴が長くなるほど、こまめなメンテナンスや定期的な健康診断が欠かせません。
日常の観察を習慣化し、病気やケガの兆候をいち早く察知できるようにしておくと良いですね。
それではまた、別の記事でお会いしましょう!
出展
- IUCN SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group [2020]
- Reptile Magazine Vol.55 [2022]
- AZA Care Manual for Testudo Species [2018]
- 日本爬虫類学会「リクガメフードガイドライン」[2021]



